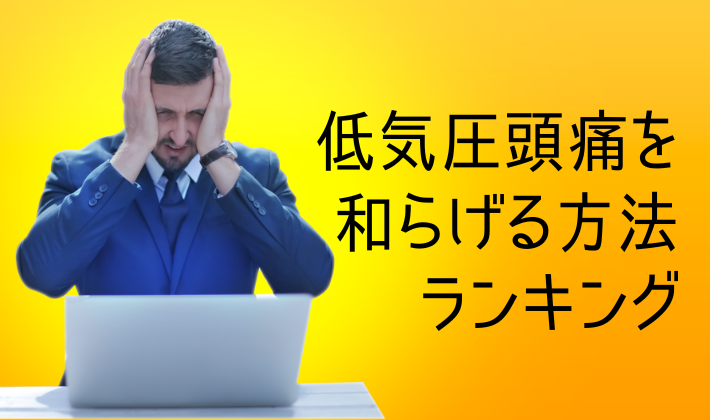こんにちは!今日は、低気圧による頭痛(天気痛)を和らげる方法を、効果的な順にランキング形式でご紹介します。気圧の変化による不調にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
※当記事では、X社の「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に則りポストを利用しております。
🥉第3位:ツボ押しで自律神経を整える
低気圧による頭痛は、自律神経の乱れが原因の一つとされています。ツボ押しは、自律神経のバランスを整え、血流を促進する効果が期待できます。以下のツボを試してみましょう。
- 合谷(ごうこく) 手の甲、親指と人差し指の骨が交わる部分のくぼみ。頭痛やだるさを和らげる効果があります。
今日は、朝から雨☔️が降ったり止んだりで一時的には降り方が強まり、気圧は昼過ぎにかけて大きく低下しそうです💣
— 野村 /DPL大阪(ダーツ教室)ダーツ講師+DPLスポーツ鍼灸院☯️院長 (@DPLtrainer) November 10, 2023
湿度も高く頭痛やめまいなどの不調が起こりやすと思われます
頭痛がある方は合谷(ゴウコク)に
お灸やツボ押しがオススメです!
睡眠や休息をしっかりとり無理せずお過ごし下さい😊 pic.twitter.com/lJv1pYDWtb
- 内関(ないかん) 手首の内側、手首のしわから指3本分下がったところ。めまいや吐き気、だるさなどを和らげます。
知らなきゃ損。東洋医学では昔から”乗り物酔いのツボ“と知られている『内関』(ないかん)。手首の手のひら側横じわの中心からひじ方向に指3本分のところ。乗り物酔い、吐き気、頭痛のツボです。二日酔い、つわりにも。精神をリラックスさせ、不眠や不安感、イライラなどを緩和する効果がありますよ。 pic.twitter.com/JD1a5KW25q
— しょうこ@病気にならない体作りを広める世界一ニコニコな鍼灸師 (@Mirai8000) March 24, 2025
- 百会(ひゃくえ) 頭頂部、左右の耳の上部を結んだ線と、顔の中央から後頭部に向かう線が交差する部分。頭痛やめまい、気分の落ち込みに効果的です。
安眠に百会ひゃくえのツボ
— 土屋幸太郎|漢方と妊活の土屋薬局|山形県東根市 (@tutiyak) April 10, 2025
ストレス社会でパソコンやスマホ、ラインなど情報が飛び交います。
頭のてっぺんには百会があり、自律神経の偏りを整え、ストレス、不眠症などの悩みの緩和にも役立ちます。
頭の疲れをツボ押しでリラックスでぐっすり睡眠いかがでしょうか?
おやすみなさい!よい夢を pic.twitter.com/5s1yoxC2HF
- 風池(ふうち) 首の後ろ、髪の生え際で、首筋の筋肉の外側にあるくぼみ。首のコリや頭痛、耳の不調に効果的です。これらのツボを、親指で5~10秒間押し、離す。これを3~5回繰り返すことで、症状の緩和が期待できます。
気圧が下がったり、雨が降ったりすると頭痛やめまいといった不調が出やすくなりますが、そんな時におすすめのツボが風池(ふうち)です。
— タカヨシィ@漢方と養生の専門家 (@takayoshiii_Rin) November 11, 2023
【風池】
・内風(ないふう)を鎮める
・風邪を取り除く
・体内の熱を冷ます
【位置】
耳の後ろの出っ張った骨と髪の生え際を結んだ中間辺りの少しくぼんだところ pic.twitter.com/V71ZpQoT01
🥈第2位:温冷療法で血行を改善
頭痛のタイプに応じて、温めるか冷やすかを選びましょう。
- 片頭痛(偏頭痛):脳の血管が拡張して痛みが発生しているため、冷やすことで血管を収縮させ、痛みを和らげます。こめかみ、首の後ろ、額などに冷湿布を貼ると効果的で。
- 緊張型頭痛:筋肉や神経が過度に緊張し血行不良が原因で起こるため、温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。首や肩、背中などを温めると効果的で。また、耳を温めることで内耳周辺の血液循環が改善され、痛みが和らぐことがあります。

ランクマニア
偏頭痛と緊張型頭痛の見分け方は?
とってもいい質問です!温冷療法は「冷やすべきか」「温めるべきか」で効果が真逆になることもあるので、自分の頭痛タイプを見極めることが大切なんです。以下に、偏頭痛と緊張型頭痛の違いをわかりやすくまとめてみました👇
🔍【偏頭痛と緊張型頭痛の見分け方】
| 特徴 | 偏頭痛(冷やす) | 緊張型頭痛(温める) |
|---|---|---|
| 🔥 痛みの強さ | 中〜強い痛み | 軽〜中程度の痛み |
| 🔁 痛みのタイプ | ズキンズキンと脈打つような痛み | ギューッと締め付けられるような痛み |
| 🔄 痛む場所 | 頭の片側が多い(左右どちらか) | 頭全体・後頭部・首筋にかけて |
| 🌈 前兆 | 視界がチカチカする、吐き気、音や光に敏感になる | 前兆はほぼなし |
| 🕰️ 継続時間 | 数時間〜3日ほど続くことも | 30分〜数時間程度(慢性的に続く人も) |
| 🧘♀️ 痛みの原因 | 血管の拡張、自律神経の乱れ、ホルモンバランスの影響など | 筋肉の緊張、姿勢の悪さ、ストレスなど |
| 💡 対応法 | 安静・暗く静かな場所・冷やす・カフェイン少量 | ストレッチ・マッサージ・温める・リラックス |
✨チェックリストで簡易診断!
✅ ズキズキして片側が痛む? → 偏頭痛の可能性大!冷やしてみて。
✅ ギューッと締め付ける感じ?両側? → 緊張型かも。温めてリラックス!
📝注意!
偏頭痛と緊張型頭痛が混合しているタイプもあるので、「冷やしたら余計痛くなった」「温めて逆にズキズキした」などがあれば、すぐに中止して様子を見ましょう。
また、慢性的だったり強い痛みが頻繁に出る場合は、一度病院で診てもらうのがおすすめです。
他にも「○○な症状なんだけど、これはどっち?」みたいな具体例があれば、もっと詳しくアドバイスできますよ!お気軽に聞いてください🧠✨
🥇第1位:生活習慣の見直しと予防策の実行
低気圧頭痛を予防するためには、日常生活の中で以下の習慣を取り入れることが効果的です。
- 頭痛ダイアリーをつける:頭痛の症状や発生時期、強さ、生活への影響、服用した薬などを記録することで、頭痛を事前に予測し、自分に合った対処法を見つけることができす。
今月の頭痛ダイアリー見返してたら、まだまだ頭痛マン健在だった😇😇
— ゆゆ子💃💃💃💃 (@yuyukoADHD) June 27, 2024
でも、前より雨や気圧に対して不安が少なくなったのは感じる。
多分頭痛の前兆や傾向わかるようになってきたことと、
新しい痛み止めを持っている安心感が大きいと思う🫶❣️ pic.twitter.com/HLG6zhPUa7
- 気圧予報アプリの活用:「頭痛ーる」などの気圧予報アプリを利用して、気圧の変化を事前に把握し、体調管理に役立てましょう。
4/13(日)の東京:低気圧が接近し、通過する影響で昼前ころには雨が降り出すでしょう。夜にかけてほぼ一日雨となりそうです。
— 頭痛ーる:気圧予報で体調管理⛅ (@terunekootenki) April 12, 2025
沿岸では風もやや強まりそうなので、ご注意ください。
気圧は夜にかけて長い時間、大きな低下が続いてしまいそうです。体調の変化に十分に気を付けてお過ごしください。… pic.twitter.com/ZQ3PgiggnS
- カフェインの適度な摂取:カフェインには血管収縮作用があり、拡張した血管を収縮させることで頭痛を緩和する効果が期待できます。コーヒーや紅茶、緑茶などを1日3~4杯程度を目安に摂取しましょう。ただし、過剰摂取は逆効果になることもあるので注意が必要です。
とにかくコーラ好きなんだが、ほら、やっぱ❤#コーラ#体調不良
— Hiroko Y (@HirokoY176964) March 25, 2025
【コーラに含まれる成分と効果】
カフェイン:頭痛や片頭痛を和らげ、気管を拡張させて呼吸をしやすくする効果があります。また、覚醒作用があり、疲労回復に役立つ可能性があります。… pic.twitter.com/5ASQNQRr2R
- 十分な睡眠と水分補給:睡眠不足や脱水症状は頭痛を悪化させる可能性があるため、十分な睡眠とこまめな水分補給を心がけましう。
【生活習慣とサプリを合わせることで頭痛を軽減】
— なみ🍆ナース (@namins_27) April 11, 2025
サプリメントだけでなく
①水分摂取
②適度な睡眠
③ストレス管理も頭痛対策には重要です。
慢性的な頭痛がある場合は、必ず医師に相談してくださいね。…
—
低気圧頭痛は、日常生活に支障をきたすこともあるつらい症状。今回ご紹介した対策を試しても改善が見られない場合は、我慢せずに専門家へ相談しましょう。自分に合った対策方法を見つけることで、症状を和らげ、快適に過ごすことができるでしう。
次回のランキングもお楽しみに!